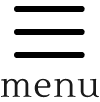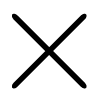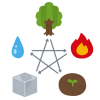雑記・症例解説
2025-11-24 16:43:00
動悸
動悸について中医学の考えを書いてみようと思います。
動悸とは心臓がいつもより速く激しく拍動する感覚です。
私の周りにも動悸を経験された方は多くいますし、過去に勤めていた鍼灸院にも動悸を訴えられる方は多くいました。
過去に私自身もプレッシャーで軽く動悸が起こったことがあり、同じ流派の鍼治療を受けたことがあります(左右どちらか忘れましたが小指の付け根のツボに一本)
動悸は中医学で怔忡(せいちゅう)と驚悸(きょうき)に分けられます。
<怔忡>
明らかな外因がなく動悸を自覚し、器質的に問題がある場合が多く症状として重いもの。
<驚悸>
驚きや焦り、いら立ち、悩みなどの精神的要素、疲労によって動悸が誘発されるもの。長引くと怔忡となる。
動悸は中医学でいう「心(しん)」の臓が深く関わります。
・突然の驚きや恐怖感を感じること、ストレスや考えすぎ、また出血、発汗過多で心を栄養する血や陰が不足してしまい不安感や動悸が起こる。
・長く患っていた病気や虚弱体質で心の気が不足し血脈の正常な運行を保持することができず動悸。
・飲食の不摂生や脾の臓、腎の臓の働きの低下で体内に痰濁・水飲(体内の余分な水分・湿気)が停滞し、心を犯して動悸。
・加齢や労倦で腎の陰が不足、心の母である肝の臓の血・陰が栄養・潤いが不足すると、心陽を抑えられず体内で燃え上がり火を制御することができず動悸
・心の運血機能が低下すると瘀血(滞った血)が形成され心脈が阻塞されることによって動悸
などがあります。
動悸するからここのツボに鍼を、灸をする!というのではなく、発生機序によって鍼灸からのアプローチも養生法も変わってきます。